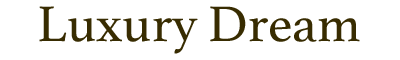ラグジュアリードリームイメージ画像
新車価格では1000万円を超えるモデルもあるレンジローバー。そんなハイエンドSUVが、中古市場では「えっ、こんなに安いの?」と驚くような価格で売られていることがあります。外観もスタイリッシュで、ラグジュアリーな内装。ブランドのイメージも申し分ない。それなのに、なぜここまで値落ちするのか。その背景には「単なるお買い得」では済まない、いくつかの理由が隠れています。
僕も一時期、本気でレンジローバーの中古を狙っていたことがあります。見た目のインパクト、ステータス感、国産車にはない雰囲気。まさに「大人の男の夢」って感じがして憧れていました。けれど調べれば調べるほど、「やめとけ」「維持できない」「壊れる」といったネガティブなワードが並び始め、不安を感じたのも事実です。けれど、それと同時に「本当にそうなのか?」という疑問も湧いてきました。
そもそも“安い”ということには必ず理由があります。日本車のように長持ちする設計とは違ったコンセプトで作られていること、整備に手間がかかること、そもそも購入層のサイクルが早いこと。そういった要因が複合的に影響して、レンジローバーは中古車になると一気に価格が下がるんです。でも、それって必ずしも「悪いこと」ではないと僕は思っています。
この記事では、「レンジローバー 中古車 安い理由」というテーマを通じて、なぜ値落ちが激しいのかという根本的な背景や、オーナーのリアルな声、そしてその先にある“本当の価値”についても掘り下げていきます。ただ安いから手を出すのではなく、納得して選ぶために知っておくべきポイントを、僕自身の視点から丁寧にお伝えしていきます。
この記事でわかること
・レンジローバー中古車が新車より極端に安くなる理由
・実際に所有した人の“やめとけ”と“買ってよかった”の本音
・故障・維持費・走行寿命などのリスクと実態
・安くても価値があると感じる人の選び方とは
レンジローバー 中古車 安い理由を探る

ラグジュアリードリームイメージ画像
街で見かけると、思わず目で追ってしまうような存在感。それがレンジローバーというクルマです。独特のオーラ、洗練されたデザイン、静かな高級感。まさに“乗っているだけで絵になる車”だと思います。そんなラグジュアリーSUVが、中古車市場では「ちょっといい国産SUVより安いじゃん」と思えるような価格で出回っていることがあります。これは車好きなら誰しも一度は「なぜこんなに安いの?」と首をかしげる瞬間ではないでしょうか。
僕自身も以前、カーセンサーを眺めていて、思わず声が出たことがありました。「新車価格1200万円超えが、今350万円?」と。もちろん走行距離はそれなりに伸びていたし、年式も5〜6年落ちでしたが、それでも価格の落差に驚いたのを覚えています。冷静に考えれば、新車で買ったオーナーが数年で800万円以上の値落ちを経験していることになります。では、なぜそんなことが起きるのでしょうか。
そこには、レンジローバーというブランドの特性と、中古車市場の需要バランス、さらにメンテナンスコストや耐久性といった要素が絡み合って存在しています。つまり「壊れやすいから安い」とか「人気がないから安い」といった単純な話ではなく、もう少し複雑で、そして“合理的”な事情があるんです。
このセクションでは、レンジローバーの中古車がなぜ新車時から大幅に価格が下がるのか、その背景や構造をひとつひとつ紐解いていきます。価格が安くなるということには、それなりの意味がある。でもそれを知ったうえで選ぶなら、もしかしたら賢い買い方だってできるかもしれません。
・新車価格とのギャップが大きすぎる理由
→ 高級ブランドなのになぜここまで値下がるのか
・故障リスクと修理費用の高さが影響
→ 電装系やエアサスの弱点とメンテナンスコスト
・中古車市場で玉数が増える背景とは
→ オーナーの買い替えサイクルとリース落ちの存在
・「維持できない」と言われる本当の理由
→ 保険・税金・燃費・パーツ価格のリアルな話
・レンジローバーは何年乗れるのか?寿命の実態
→ 走行距離と経年劣化の傾向、長く乗るには何が必要か
新車価格とのギャップが大きすぎる理由
レンジローバーの中古車を見て「これ、半額どころか3分の1以下じゃないか…」と驚いた経験がある人は多いと思います。新車価格で1000万円を超えるようなモデルが、数年落ちで300〜400万円台。それが“安すぎる”と感じる一方で、「これは何か裏があるんじゃ…」と疑ってしまうのも当然かもしれません。
この価格ギャップの大きさには、まず“ブランド価値と実質的な耐久力のギャップ”が影響しています。レンジローバーはデザイン性や快適性に優れている一方で、日本市場においては「壊れやすい」「維持費が高い」というイメージが根強く残っています。そのため、年式が5年以上経過した個体になると需要が急激に減り、価格が大きく下がってしまう傾向があるんです。
また、ランドローバー社の車両は欧州ではリース利用が多く、3〜5年で市場に放出される個体が一気に増えます。その結果、日本にも一定数が輸入されてくることで中古市場の玉数が多くなり、供給過多によって相場が押し下げられるという構図ができています。つまり、「欲しがる人は限られているのに、台数は多い」というアンバランスが価格を安くしているわけです。
さらに、国産車と違って「10年乗っても安心」という長期耐久性への信頼感が薄いのも、価格に現れています。たとえ走行距離が少なくても、「電子系が壊れるかも」「修理に時間とお金がかかるかも」といった不安が買い手のブレーキになってしまう。これが、結果的に新車価格からの急激な値落ちへとつながっているんです。
僕自身も、中古のヴォーグ(フルサイズモデル)に本気で惹かれた時期がありました。でも調べれば調べるほど「安い理由」が見えてきて、それに納得できるかどうかが選ぶ基準になるなと感じました。価格が落ちるのは“理由があるから”。けれど、それが自分にとって許容できるものであれば、むしろチャンスだとさえ言えるのかもしれません。
故障リスクと修理費用の高さが影響
レンジローバーの中古価格が大きく下がる理由として、多くの人が口をそろえて挙げるのが「故障の多さ」と「修理費の高さ」です。これは僕自身も実際に整備士の知人やオーナー経験者から何度か聞かされていたことで、興味があってもなかなか手が出なかった大きな理由のひとつでした。
特に指摘されやすいのが、電装系やエアサスペンションのトラブルです。エアサスがへたって車高が不安定になるとか、ドアロックの電子制御が誤作動するとか、ちょっとした電子系トラブルが地味に多いという話はよく聞きます。しかもこの手の故障は、部品代だけでなく工賃も高額になりがちで、ちょっとした修理でも数十万円単位になることがあるんです。
さらに厄介なのが、国産車のようにどの整備工場でもすぐ対応してもらえるわけではないという点。輸入車に強い専門のショップか、ディーラーに頼る必要があるため、トラブルが起きたときに対応できる選択肢が限られてしまいます。地方に住んでいる場合は、それだけで修理にかかる時間と費用がかさむリスクもあります。
あと地味に見落とされがちなのが、部品の輸入コストと納期です。たとえば純正の足回り部品やセンサーなどは、本国オーダーになるケースも多く、1ヶ月待ちなんてことも珍しくありません。これがユーザーの「めんどくさい」「不安」という印象に直結していて、結果的に中古車としての需要を押し下げている側面もあるんですよね。
もちろん、すべてのレンジローバーが壊れるわけではないですし、きちんとメンテナンスされていれば長く乗れる個体もたくさんあります。でも、「もし壊れたら?」という心理的なプレッシャーが価格に反映されやすいのは事実です。僕自身も購入を検討していたとき、ネットで「修理代100万円超えました」なんて体験談を読んでしまい、一瞬で現実に引き戻されたことがありました。
安くなっている背景には、こうした“隠れた維持コスト”への不安が常につきまとっているという現実があります。買う前にそれを理解できていれば、驚くこともなく、むしろ冷静に判断ができるかもしれません。
中古車市場で玉数が増える背景とは
レンジローバーの中古車が“安い”と感じる大きな理由のひとつに、中古市場における台数、いわゆる「玉数(たまず)」の多さがあります。そもそも流通している車の数が多ければ、それだけ選択肢は広がりますし、価格競争も起きやすくなります。でも、なぜあれほど高額なレンジローバーが、中古車市場でこんなに多く出回っているのでしょうか。
まずひとつにあるのは、欧州を中心に「リース契約で3〜5年乗って返却する」という使われ方が多いという事実です。ランドローバーは英国をはじめ、ドイツや北欧でも企業や個人リース契約の割合が高く、一定年数での買い替えが前提になっているんですね。そのため、状態の良い中古車が定期的に大量に市場に放出されるというサイクルができあがっています。
また、日本国内においても「数年乗って乗り換える」というオーナーが多い車種でもあります。これは、レンジローバーの購入層が比較的経済的に余裕のある層であることが影響していると考えられます。飽きる前に次の車に乗り換える、あるいは最新のモデルに更新するというライフスタイルの中で、手放された車がどんどん中古市場へ流れていく構造です。
さらに、レンジローバーの中でも人気の高いヴェラールやイヴォークといったモデルは、販売台数も多いため自然と中古台数も増えていきます。しかも、ディーラーが販売する認定中古車だけでなく、輸入業者が扱う並行輸入車まで含めると、選べる車両の幅はかなり広くなっています。その結果、「条件の良い車がたくさんある」という状態が、中古価格を下げる圧力にもなっているのです。
僕が中古車サイトでレンジローバーを調べたときも、年式・距離・グレードを絞ってもかなりの数がヒットして、逆にどれが本当に“お買い得”なのか迷ってしまったほどです。車は希少性があるほど価値が落ちにくいですが、逆に供給が多いと価格競争が避けられません。
つまり、中古市場での価格の安さは、車そのものの“人気のなさ”ではなく、むしろ流通のサイクルが安定していて供給が多いという構造的な理由が大きいんです。その背景を知っておくことで、目の前の価格だけに惑わされず、冷静に選ぶ判断ができるのではないでしょうか。
「維持できない」と言われる本当の理由
レンジローバーの中古車を調べていると、かなりの確率で目にするのが「維持できない」「庶民が手を出すべきじゃない」といった声。価格が下がって手が届きやすくなったとはいえ、なぜここまで“維持の大変さ”が語られるのでしょうか。僕自身も過去に真剣に購入を検討していた時期があり、そのときに直面した現実が、まさにこの“維持の壁”でした。
まず第一に、税金・保険料の高さがあります。排気量が3.0Lや5.0Lと大きめなモデルが多く、当然ながら自動車税も高額。加えて任意保険の料率も高くなりやすく、車両保険をつければ年間20万〜30万円になることも珍しくありません。購入直後のテンションでは許容できても、数年維持していく中でじわじわと効いてくるコストです。
次にネックになるのが燃費の悪さ。街乗り中心だとリッター5〜6km程度しか走らないケースも多く、ガソリン代が想像以上にかかります。特にハイオク仕様のモデルが多いため、毎月の給油コストも国産車とは桁が違います。これに加えて、エンジンオイルやタイヤなどの消耗品も高級車ならではの価格設定。維持費が“じわじわ効いてくる”というのはこういうことなんですよね。
そして忘れてはいけないのが修理費と部品代。先ほども触れましたが、レンジローバーは電装系やエアサスのトラブルが比較的多く、修理には純正部品の取り寄せが必要になることが多いです。しかも部品代が高いだけでなく、交換にかかる工賃も高額になりがち。ちょっとした不調が「30万円コース」なんていう話もリアルに耳にします。
さらに、地方在住者にとっては整備環境の制限も課題になります。国産車のようにどこの整備工場でも受け入れてくれるわけではなく、輸入車に強いショップや正規ディーラーでないと対応できないことも。そのたびに遠方まで持ち込む必要が出てきて、時間的コストもかかるというわけです。
こうした維持費の高さや手間の多さが、“庶民が手を出すべきではない”という印象を強くしているのでしょう。でも裏を返せば、そうした点を理解したうえで「それでも欲しい」と思えるかどうか。それこそが、レンジローバーを所有する価値観の分かれ目なのかもしれません。
レンジローバーは何年乗れるのか?寿命の実態
「この車、何年くらい乗れるんだろう?」というのは、中古でレンジローバーを検討している人が最も気になる点のひとつだと思います。新車時の価格が高いだけに、中古とはいえ長く乗り続けたいという気持ちは当然ありますよね。僕自身も一時期、本気で10年は乗るつもりで中古のヴェラールを検討していました。でも、そこには意外な“壁”がいくつかあったんです。
まず前提として、レンジローバーは構造的には長く乗れるポテンシャルを持った車です。エンジンやシャシーの基本構造は堅牢ですし、海外では20万km以上乗っているユーザーも珍しくありません。ただし、その前に立ちはだかるのが“維持費”と“トラブル耐性”。これが寿命に大きく影響してくるのが実情です。
実際のところ、日本国内でのレンジローバーの「寿命」は、10年または10万km前後を境に買い替えられるケースが多いようです。これは物理的な限界というより、修理や部品交換にかかるコストの増加にオーナーが折り合いをつけられなくなるパターンが多いから。たとえば10年落ちでエアサス交換、電装系修理、タイヤとブレーキ周りで一気に50万円以上かかるとすれば、「もう乗り換えようかな」となる気持ちはわかります。
また、最新のモデルほど複雑な電子制御が多く、それが寿命に影響することもあります。昔のように「メカを直しながら乗る」では済まず、モジュール単位でしか交換できない部品が多くなると、寿命=コスト許容の限界、という構図が見えてきます。
一方で、しっかり整備履歴のある個体や、こまめにメンテナンスされてきた車は、10年を過ぎてもコンディション良好なものも多いです。実際、正規ディーラーの認定中古車では7年落ちでも保証付きで販売されているケースもあり、状態次第ではまだまだ長く乗ることは可能です。
つまり、レンジローバーの寿命は“構造的寿命”というより“経済的寿命”といえるかもしれません。修理代に納得できるか、乗り続ける価値を自分がどう判断するか。その覚悟と相性が、この車の寿命を決めるのだと僕は思います。
レンジローバーの中古はやめとけ?それでも惹かれる人の理由

ラグジュアリードリームイメージ画像
「レンジローバーの中古はやめとけ」——ネットでこの車を検索すると、そんな言葉がたびたび目に入ってきます。確かに、故障リスクや維持費の高さを考えると、“軽い気持ちで選ぶべき車ではない”という意見には一定の説得力があります。でもそれでも、いや、それだからこそ、レンジローバーに惹かれる人たちがいるのもまた事実です。
僕もかつてはそのひとりでした。国産SUVでは得られないあの特別感、街中でもアウトドアでも映えるデザイン、内装のラグジュアリーさ、そして何より“クルマに乗る時間を自分にとっての非日常にしてくれる感覚”。たとえリスクがあっても、それを超える何かがあるんじゃないか、そう思わせる不思議な魅力がこの車にはあるんです。
よく「車は道具」と割り切る人もいますし、合理性を追い求めれば国産SUVの方が圧倒的に安心でコスパも高い。それでも、機能や燃費だけでは測れない“感情を動かす価値”というのは、車選びにおいて決して無視できないものではないでしょうか。ましてや車好きにとっては、「壊れるかも」すらも“味”として受け入れてしまう感性があったりもします。
SNSやYouTubeのレビューを見ていると、「買って後悔した」と語る人がいる一方で、「いろいろあるけど、それでも乗ってよかった」と語る人も一定数存在しています。そこには、“モノとしての価値”ではなく、“経験としての価値”を求めてレンジローバーを選ぶ姿勢がにじんでいて、僕自身その考え方にかなり共感しました。
このセクションでは、あえて“やめとけ”と言われる理由の裏にある“それでも乗りたい人の本音”に焦点をあててみようと思います。ネガティブな側面を理解した上でなお惹かれる人には、やはり共通する価値観やライフスタイルの傾向があります。その視点から、レンジローバーという車がなぜ人を惹きつけてやまないのかを、改めて紐解いていきましょう。
・「やめとけ」と言われても選ぶ人の特徴とは
→ ステータス性、趣味性、クルマとの付き合い方の違い
・実際に乗って後悔した人・しなかった人の違い
→ オーナーレビューやSNSのリアルな感想を分析
・「走る宝石」とも呼ばれる唯一無二の魅力
→ デザイン・内装・存在感の高さは他にない強み
・安い中古を選ぶ際の注意点と見極め方
→ 年式・走行距離・整備記録・保証付き物件の選び方
・リセールを気にせず“自己満足”で選べる人へ
→ 短期的な損得よりも、所有体験そのものに価値を感じる視点
「やめとけ」と言われても選ぶ人の特徴とは
レンジローバーの中古車を検討していると、ネットや知人から「やめとけ」という言葉を耳にすることがあります。確かに、故障リスクや維持費の高さを考えると、万人に勧められる車ではないのは事実です。でも、そういった警告を受けても、むしろ「それでも乗ってみたい」と強く惹かれる人たちがいるのもまた事実。そういった人たちには、いくつかの共通した特徴があるように感じます。
ひとつは、実用性よりも「所有することの意味」に重きを置いている人です。車を単なる移動手段ではなく、「自己表現」や「ライフスタイルの一部」として考えている人にとって、レンジローバーの持つデザインやオーラは大きな魅力になります。多少の手間やコストを引き受けても、それに見合う満足感があると感じている人たちです。
次に多いのが、クルマ好き、あるいは“クセのある車”を愛するタイプの人。国産車の完成度の高さには満足できない、あるいは“ちょっと面倒な部分すらも愛せる”というような気質の持ち主。レンジローバーはある意味“付き合いがいのある車”とも言えるので、乗っていて飽きがこない、トラブルも含めて「味がある」と感じるような人には刺さります。
また、一定以上の収入や資産があり、「壊れてもなんとかなる」余裕を持っている人も多い印象です。これは経済的な問題だけではなく、精神的な余裕も含まれます。細かいトラブルで一喜一憂するよりも、「そんなこともあるよね」と受け入れてしまえる柔らかさ。それがあるからこそ、レンジローバーという車を“楽しめる”のだと思います。
僕の知人にも、フルサイズのレンジを2台乗り継いでいる人がいます。彼は「壊れる前提で買ってる」と笑って話していましたが、そのぶんトラブル時の対応にも慣れていて、むしろ“道楽”として楽しんでいる様子でした。そんなふうに、クルマとの付き合い方そのものが違うんですよね。
つまり、「やめとけ」と言われても選ぶ人たちは、単に情報を鵜呑みにするのではなく、自分なりの価値基準を持ち、そこに合致するものを選んでいる。リスクを理解したうえで、それでも手に入れたいと思えるかどうか——そこに、レンジローバーという車の本質があるのかもしれません。
実際に乗って後悔した人・しなかった人の違い
レンジローバーの中古車に関して、「買って後悔した」という声もあれば、「最高の相棒だ」と語る人もいる。この両極端な評価は、ある意味この車の本質をよく表しているように思います。そして、実際に乗った人たちの体験談を追っていくと、後悔する人・しない人には、いくつかの明確な“違い”があるように見えてきます。
まず、後悔する人に多いのは、「価格が安いから」という理由だけで飛びついたパターンです。中古価格の魅力に惹かれ、「高級車がお得に買える」と期待して購入したものの、維持費や修理費の現実を知って一気に熱が冷める。エアサスの故障やエンジンチェックランプの頻発、タイヤやオイル交換の出費…想像よりも遥かにお金がかかると感じてしまうのです。そういった人たちは、“高級車を所有する前提の覚悟”ができていなかったケースが多い印象です。
一方、後悔していない人たちはというと、初めからある程度のリスクを理解し、その上で選んでいるのが共通しています。「壊れる可能性もあるけど、その分手をかける楽しさがある」とか、「整備にお金がかかるのは承知していたし、それも含めてこの車に乗ってる」というスタンス。クルマとの付き合い方を“合理性”よりも“愛着”や“感情”で選んでいる人は、たとえトラブルがあっても後悔という言葉に至らないのだと思います。
また、後悔していない人は信頼できる整備環境を確保していたり、保証付きの個体を選んでいたりすることも多いです。購入前にディーラーで点検内容を確認したり、車歴や修理履歴をしっかりチェックするなど、事前準備を怠らない。こうした“安心材料”があることで、たとえトラブルが起きても冷静に対処できるんですよね。
僕自身がSNSで調べていたときも、「後悔した」という人の多くは、“想像以上に金がかかった”という経済的な要因が強く、「それでもこのスタイルが好き」という人は、苦労も楽しさのうちと語っていました。
つまり、後悔するかどうかは、車そのものではなく「どういう気持ちでこの車と向き合っているか」が大きな分かれ道になるということ。レンジローバーは、スペック以上に“付き合い方”が問われる車だと実感します。
「走る宝石」とも呼ばれる唯一無二の魅力
「壊れる」「維持費が高い」…そんなネガティブな声が絶えないレンジローバーですが、それでもこの車が人々を惹きつける理由はどこにあるのか。それを一言で表すとするならば、“走る宝石”という表現が一番しっくりくるかもしれません。これは実際に、英国ではジャガー・ランドローバーをそう呼ぶ人が少なくないほどで、まさに“機械でありながら芸術品”のような存在なのです。
まず目を奪われるのが、そのデザイン性。都会的で洗練されているのに、どこか重厚感があって、一目で「ただ者じゃない」と分かる存在感があります。ヴェラールやイヴォークのようなモデルは、SUVでありながらクーペのようなラインを持ち、リアフェンダーの張り出しやフロントマスクのバランス感覚は、国産車や他の欧州車とは明らかに一線を画しています。
そして内装に目を向けると、そのラグジュアリーさにも驚かされます。上質なレザーやウッドパネルの使い方、静粛性の高さ、全体の造形バランス。見た目だけでなく「触れて気持ちがいい」と感じさせる空間作りが、確実に日常を格上げしてくれます。助手席に乗った人が自然と「うわ、すごいね…」とつぶやく、その反応だけでも、この車の“持つ力”を実感することができるでしょう。
僕も試乗したとき、ドアを閉めた瞬間の「バフッ」という静かな閉まり音と、エンジンをかけたときの低く澄んだ音に鳥肌が立ちました。豪華さの中に無理のない品格があるというか、“高級感”を押し付けないのに、しっかり感じさせる。それって案外難しいことで、だからこそレンジローバーは特別なんですよね。
それに、デザインや内装の話だけではなく、乗っていると“扱われ方”まで変わるという声もあります。駐車場での視線、レストランのバレーパーキングでの扱い、すれ違うときの周囲の反応。クルマを通じて得られる“ちょっとした優越感”は、日常をほんの少し特別に変えてくれるものです。
そう考えると、レンジローバーの魅力は「機能がどう」とか「燃費がどう」といった話を超えているのかもしれません。宝石のように、理屈ではなく“美しさ”や“ときめき”に価値を感じる人にこそ、このクルマの本当の意味が伝わるのだと思います。
安い中古を選ぶ際の注意点と見極め方
レンジローバーの中古車を見ていると、年式やグレードによっては「えっ、こんな価格でいいの?」と思うような掘り出し物に出会うことがあります。でも、価格の安さだけで飛びついてしまうのは危険。レンジローバーという車は、見た目や価格以上に“中身”をきちんと見極めることが求められるクルマです。僕自身も購入を検討していた際、「これは買ってもいい個体なのか?」という判断にとても悩みました。
まず大前提としてチェックしたいのが、**整備記録(メンテナンス履歴)**です。どんなに見た目が綺麗でも、きちんと点検・修理がされていない個体は避けるべき。特にエアサスの交換歴、ミッションや電子制御系の修理歴など、故障が多い部位に関して履歴が残っている車は安心材料になります。逆に、履歴がまったくない車は、価格が安くても手を出しにくいです。
次に注目したいのは、保証の有無。認定中古車や専門ショップで販売されている保証付きの車両であれば、万が一のトラブル時にも費用を抑えられる可能性があります。保証期間が短くても「初期トラブルを防げる」ことが大きなメリット。逆に、無保証で格安販売されている個体は、修理リスクも含めて“すべて自己責任”になります。
走行距離にも注意が必要です。一般的に「輸入車は5万kmが境目」と言われることもありますが、レンジローバーの場合は7〜8万kmを超えると一気に修理リスクが高まる傾向があります。これは構造上の消耗や、年数による電子パーツの劣化が原因。もちろん、しっかり整備されていれば問題ないですが、そうでない場合は急な出費につながる可能性が高いです。
また、並行輸入車か正規ディーラー車かという点もチェックしたいポイント。並行輸入車は価格が安い反面、パーツの仕様が異なったり、保証・整備の面で不安が残る場合もあります。初めてレンジローバーに乗る方には、なるべく正規ディーラー車の履歴がはっきりした車両をおすすめしたいですね。
安い中古車を上手に選ぶには、価格だけでなく「なぜ安いのか?」という理由に目を向けること。そして、その理由が納得できるものであれば、それは“安物”ではなく“賢い選択”になるかもしれません。
リセールを気にせず“自己満足”で選べる人へ
車を買うとき、どうしても頭をよぎるのが「売るときにいくらになるか?」というリセールバリューの問題です。特に日本では、資産価値や売却時の損得を重視する傾向が強いため、「リセールが悪い車は選ばない方がいい」という考え方も根強くあります。でも、レンジローバーのような車を選ぶとき、その価値観は少し脇に置いてもいいんじゃないかと思うんです。
というのも、レンジローバーの中古価格は確かに落ちやすい。数年乗ってから売ろうと思っても、購入時の半額以下になることも珍しくありません。リセールを気にする人にとっては、これは大きなデメリットでしょう。でも逆に言えば、だからこそ**「損得を超えて本当に好きな車を選ぶ」**という選び方ができるとも言えるんです。
僕の知人にも、新車でヴォーグを購入し、7年乗って走行距離10万kmを超えても「まだ手放す気になれない」と話す人がいます。リセールなんて考えたこともないそうで、「この車で毎日を過ごす満足感の方がよっぽど価値がある」と言っていたのが印象的でした。こういう選び方って、ある意味とても豊かだなと思います。
もちろん、リセールを無視するには、それなりの金銭的余裕が必要です。でもそれ以上に、「この車に乗ること自体が自分の気分を高めてくれる」とか、「このデザインと内装に毎回ワクワクする」といった、“自己満足のための投資”として割り切れるかどうかが大切なんじゃないでしょうか。
世の中には、燃費が良くて壊れにくくて、リセールも良い車がたくさんあります。でも、心が動かされるかというと、そうでもなかったりしますよね。レンジローバーは、そういう“理屈では測れない”部分に全振りしたような車。だからこそ、選ぶ人も「合理性よりも、自分がどう感じるか」を重視できる人が向いているんだと思います。
リセールを気にして選ばなかった車と、リセールを気にせず選んだ車。10年後に振り返ったとき、「こっちでよかった」と思えるのは、案外後者かもしれません。そう思える車に出会えること自体が、クルマ好きにとっては幸せなことなんです。
まとめ:レンジローバー 中古車 安い理由を知って納得の選択を
レンジローバーの中古車が「安い」と感じられる背景には、単なる人気の有無や性能の話では収まりきらない、奥深い事情があります。高級車としてのステータスを持ちながら、年数が経つとともに価格が一気に落ち込む。その理由は、維持費の高さ、トラブルのリスク、そして消耗部品や電子制御系の複雑さなど、現実的なコストが絡んでいるからこそです。
ただ、それは“ダメな車”だから安いのではなく、“手間がかかる車”だから価格が調整されているというだけのこと。実際、そのリスクを承知のうえで選ぶ人たちは、自分なりのスタイルやこだわりを持ち、「所有すること」自体を価値として楽しんでいます。
僕自身もレンジローバーという車に惹かれたひとりとして、安くなっている理由を理解したうえで、それでも「乗ってみたい」と思えるかどうかが大切だと感じました。価格に現れない価値を感じられるかどうか、それがこの車との相性の分かれ目なのかもしれません。
すべてが合理的な選択ではないけれど、自分の感性を信じて選ぶ一台があってもいい。レンジローバーの中古車は、そんな“感情のスイッチ”を押してくるような存在だと思います。