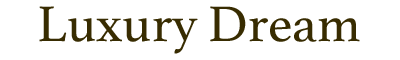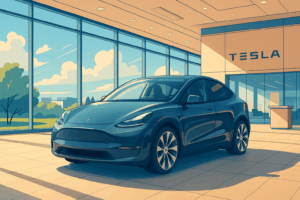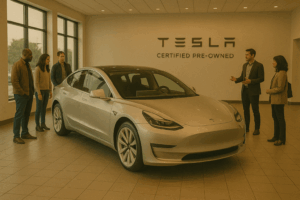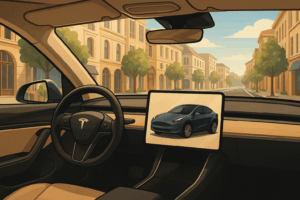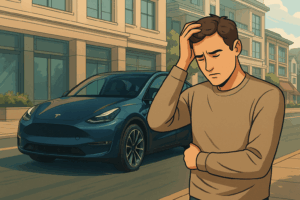ラグジュアリードリームイメージ画像
テスラはすべての人にとって“最高のクルマ”ではありません。
確かに革新的なEV技術や自動運転、ミニマルなデザインに惹かれて購入する人も多いですが、その一方で「やめとけばよかった」「正直、後悔している」という声がネット上には多数見られます。
私の周囲でも実際にテスラに乗っていた人が何人かいますが、そのうちの一人は納車後すぐにパネルのズレや作動不良を経験し、アフターサービスの不満から1年も経たずに手放しました。
一方で、「あれはアメリカ車だと割り切れば納得できるレベル」と言いながら気に入って乗り続けている人もいて、後悔するかどうかは“受け取り方と期待値”の違いにも大きく左右されると感じています。
ではなぜ、テスラは「やめとけ」「後悔する」と言われてしまうのでしょうか?
その理由は一つではなく、品質のバラつき、サポート体制の不安定さ、独特の操作系、好みが分かれる内装、そしてクチコミや評判の過熱報道など、複数の要素が絡んでいます。
特にテスラは日本の従来メーカーとはかなり異なる発想で車づくりをしているため、それを知らずに買うと「え、これが1,000万円の車?」と感じてしまうことも。
逆に、その自由さや尖った部分を理解し、愛せる人には魅力的な選択肢にもなります。
この記事では、実際に「テスラをやめとけ」と言われる原因を冷静に整理し、本当に後悔しないための選び方や、向いている人・向いていない人の特徴まで掘り下げてご紹介します。
これから購入を検討している方が、後悔しない決断を下せるよう、リアルな声と筆者の視点を交えながら解説していきます。
この記事でわかること
・テスラを「やめとけ」と言われる代表的な理由とその実態
・購入後に後悔した人のリアルな体験談や意見
・テスラの品質・サポート面での注意点
・テスラに向いている人と、向いていない人の違い
・後悔しないために購入前に確認しておくべきポイント
U-Twentyチャンネル:引用元
テスラはやめとけ・後悔したと言われる理由とは?

ラグジュアリードリームイメージ画像
テスラは近未来的なデザインと最先端のEV技術で、多くの人を魅了してきました。特にモデル3やモデルYの登場により、価格帯も身近になり、一気にユーザー層が広がりました。しかしその一方で、「テスラはやめとけ」「買って後悔した」といった声も目立ちます。
こうした否定的な意見の中には、EVという新しいジャンルへの理解不足や、テスラ特有の思想・設計へのミスマッチがある一方で、明確な弱点や注意点があることも事実です。とくに日本人がこれまで慣れ親しんできたトヨタやレクサス、ドイツ車のような“完成度”を期待してしまうと、ギャップを感じてしまう部分も多くあります。
では、具体的にどこで「やめとけばよかった」と感じるのか?まずは最もよく聞く理由の一つ、「品質の問題」から見ていきましょう。
・品質が悪い?チリズレ・内装仕上げ・経年劣化の実態
→ パネルのズレ、シート素材の安っぽさ、経年による劣化の早さなどを実体験ベースで解説。
・納車トラブルやアフターサービスに不満の声も
→ 納期遅延、サポートの対応の悪さ、修理の遅さなど「やばい」と言われる要因を整理。
・走りはいいけど音がない?静かすぎるEVの“味気なさ”
→ 加速力や静粛性の裏にある「運転していてつまらない」と感じる人の意見を紹介。
・操作が独特すぎる?タッチパネルと物理ボタンの不在
→ すべてが画面操作、戸惑いや使いにくさの声、年配層・初心者への不親切さに言及。
・嫌われる理由とは?SNSでのアンチや偏見の現実
→ 「テスラ乗り=意識高い系」「マナーが悪い」などイメージからくる否定的な声の背景。
品質が悪い?チリズレ・内装仕上げ・経年劣化の実態
テスラに対して「品質が悪い」と言われる理由の一つが、パネルのチリ(隙間)や内装の仕上げ精度の低さです。
実際に納車されたばかりの新車でも、ドアパネルのズレや左右非対称の隙間、塗装のムラなどが見つかることは珍しくありません。ネット上では「パネルズレ選手権」などと揶揄されるほど、ユーザーの間でもネタにされてしまうレベルです。
特に日本車やドイツ車のような「ミリ単位で整った造り」に慣れているユーザーにとって、こうした粗さは強い違和感を覚える部分。**「1,000万円近いモデルSでこれはない」**という声も、SNSやレビューサイトで頻繁に見かけます。
内装の質感についても同様で、テスラのインテリアは非常にミニマルな設計である反面、プラスチックの質感やレザーの縫製などがチープに感じられることも。ドアの内側やダッシュボード、シートの触感など、日常的に触れる部分の質感が期待外れだったと感じる人も多いです。
さらに、経年劣化の早さも指摘されています。筆者の知人でモデル3を3年所有していた方は、シートのサイドサポート部分がすでにひび割れており、「こんなに早く劣化するのは初めて」と驚いていました。また、天井の内張りの浮きや、トリムパーツの剥がれなども一部で報告されています。
このように、テスラの品質に対する評価は、価格帯とのバランス感にズレを感じる人が多いのが現実です。高価格帯のEVという期待値で購入した結果、「これなら他の車にすればよかった」と後悔してしまう…そんな構図が、「テスラはやめとけ」と言われる原因のひとつになっています。
もちろん、「アメリカ車だからこんなもん」「性能が全てだから気にしない」という割り切り方もありますが、細部の完成度や信頼性を重視する人にはストレスになるポイントでもあるのです。
納車トラブルやアフターサービスに不満の声も
テスラに関して「やめとけ」と言われる理由の中でも、購入後の体験、特に納車トラブルやアフターサービスへの不満は非常に多くのユーザーが口をそろえて挙げるポイントです。これは「車そのものの良し悪し」ではなく、「企業としての体制」に由来する問題が多いため、購入前に必ず把握しておくべき項目です。
まずよく聞くのが、納車時の不具合や遅延。
たとえば、「納車日に行ったら車が届いていなかった」「登録ミスで納車が数週間ずれた」など、基本的な業務フローにミスが多く、ユーザーが不安や不信感を抱くケースが後を絶ちません。SNS上でも、「納車日に4時間待たされた」「納車直後にドアハンドルが開かなくなった」というような投稿は珍しくなく、“プレミアムカーの納車体験”とは程遠い対応にがっかりする人も多いです。
次に問題になるのが、サービスセンターや修理体制の脆弱さ。
日本国内には限られた数のテスラサービスセンターしかなく、地域によっては**「片道2時間以上かけて修理に出す」**という人もいます。しかも予約が取りにくく、ちょっとした不具合でも数週間先まで対応できないというケースも多く報告されています。
一例として、筆者の知人がモデルYを購入した際、走行中に突然エラーメッセージが出て自動停止。すぐにカスタマーサポートに連絡したものの、対応はチャットのみで電話不可、しかもトラブル内容に対する的確な回答は得られず、レッカーの手配にも時間がかかり非常に苦労していました。
このように、テスラは「スマホのようにオンラインで完結するサービス」を目指してはいるものの、“クルマという命を預ける商品”に求められる対面サポートや即応性が著しく不足しているという印象を持つ人も少なくありません。
また、修理費用やパーツ供給に関してもネガティブな声が多くあります。
日本におけるテスラの修理は正規工場に限られ、社外工場では対応できないパーツやソフト制限が多いため、「修理費が高い・納期が長い・融通がきかない」という三重苦を感じることも。これにより、「故障したら終わり」「車検通すのが怖い」といった心理的負担を抱えるユーザーも増えています。
さらに、テスラでは「代車文化」が基本的に存在せず、修理のために車を預けても代車なしで生活に支障をきたすという点も、国産ディーラー慣れしている人には大きな不満ポイントです。
結局のところ、テスラは車そのものではなく、「買ってからの体験」で後悔してしまう人が多いというのが実情です。
とくに「アフターサービスは当たり前に手厚いもの」という日本的な期待値を持っていると、そのギャップに驚かされるでしょう。
走りはいいけど音がない?静かすぎるEVの“味気なさ”
テスラの走行性能に対しては、多くの人が口を揃えて「速い」「スムーズ」「力強い」と高評価を与えています。特にモデル3やモデルYのロングレンジ、そしてパフォーマンスモデルに関しては、0-100km/h加速が3〜4秒台と、スポーツカー顔負けの性能を持っています。
ガソリン車では体感できない瞬時のレスポンスは、一度味わうと病みつきになるという声も多く、EVならではの走りの“気持ちよさ”は確かに存在します。
しかし、その一方で「運転がつまらない」「味気ない」という声が上がっているのも事実。
なぜこれほど高性能でありながら、後悔の原因になってしまうことがあるのでしょうか?
一番の理由はやはり、EV特有の“無音”に近い走行感です。
ガソリン車に慣れている人にとって、加速時のエンジン音やギアの変速による“演出”は、ドライビングの楽しさの一部です。特にスポーツカーやプレミアムセダンを乗り継いできた方にとっては、「音と加速がリンクすることで感情が高まる」ことに価値を感じている場合が多いでしょう。
ところが、テスラではアクセルを踏んでもほぼ無音。変速ショックもなく、**“音や振動がないことによる物足りなさ”**を感じてしまう人が一定数いるのです。
これはEV全般に言えることですが、**とくにテスラは室内静粛性も高いため、ドライビングが極めて“フラットな感覚”**になりがちです。
その結果、「移動手段としては快適だけど、ワクワク感がない」といった評価につながりやすくなります。
さらに、ステアリングフィールやブレーキのタッチも、人によっては「人工的」「曖昧」と感じることがあります。
これはテスラがソフトウェア制御を多用している影響で、ハンドリングやブレーキの感覚も電子的にチューニングされており、“生の手応え”を求める人には少し味気なく映ってしまうのです。
また、走行音やフィーリングの演出がほとんどないため、**「気づいたら法定速度を超えている」「スピード感覚がつかみにくい」**という副作用もあります。これも一部ユーザーにとってはストレスの原因となり、「乗ってて緊張する」「疲れる」といった評価に直結することも。
筆者の知人で以前BMW M3に乗っていた方が、テスラ モデル3パフォーマンスに乗り換えたところ、「確かに速いけど、感覚的には全く高揚感がない。乗ってて感情が動かない」と語っていたのが印象的でした。
逆に、「静かで刺激がないからこそ、落ち着いて運転できる」と感じる人もいますが、これは好みが大きく分かれるポイントです。
つまり、テスラの「走りの良さ」と「ドライビングの楽しさ」は必ずしも一致しないということ。
スペックだけを見て選ぶと、「あれ?思ってたのと違う」と後悔につながることもあるため、自分が車に何を求めているのかを明確にしておく必要があります。
操作が独特すぎる?タッチパネルと物理ボタンの不在
テスラに初めて乗った人が戸惑うポイントのひとつが、「物理ボタンの少なさ、そして操作のすべてがタッチパネルに集約されていること」です。
これは“未来的”“ミニマルデザイン”といえば聞こえはいいのですが、実際の使い勝手の面では「不便」「危険」といった否定的な意見も根強くあります。
まず、テスラ車は他の自動車と違って、エアコンの風向きやドアミラーの調整、ワイパー設定、ライト操作などまでもがセンターの大画面(通称:iPad)を介して行う必要があります。
操作感はスマホのようで直感的といえばそうなのですが、運転中にこうした細かい設定をタッチ操作で行うのは、視線移動や注意力が分散されるリスクも大きく、慣れないうちは非常に不安を感じるユーザーも多いです。
たとえば、「ワイパーを1段階だけ強くしたい」「エアコンの風量を1だけ上げたい」といった、普通ならダイヤルやボタンで即座に対応できる操作であっても、テスラではタップ→スライド→確定という手順を踏まなければならないこともあります。
そのたびに視線が前から外れるため、「操作しながらの運転が怖い」「雨の日の運転がストレス」という声も少なくありません。
また、インフォテインメントの安定性や反応速度にバラつきがあることも問題です。
ソフトウェアアップデートによって頻繁に仕様変更がされるため、ある日突然ボタンの位置や動作が変わっていて「慣れた操作ができない」というケースもあります。これを“進化”と受け取れるか、“混乱”と感じるかは人それぞれですが、クルマに変化より安定を求める人には向かない特徴です。
もうひとつ見逃せないのが、「高齢者や運転初心者にとっては使いにくい設計」であるという点です。
ボタンやスイッチで感覚的に操作できる車に慣れた人が、急に“画面の中のUIで操作する”という文化に入ると、機能はあっても使いこなせない=使えないという事態に陥ることも。
これは「車がスマホ化している」とも言えますが、“誰でも安心して使える車”という視点から見れば、大きな課題でもあります。
筆者自身、試乗した際に驚いたのが、「グローブボックスすらタッチパネルで開ける」という仕様。ほんの些細なことですが、「これは便利なのか?それとも不便なのか?」と戸惑った記憶があります。
このように、タッチパネル中心の操作系統は、革新性と引き換えに“使いやすさ”を犠牲にしている側面もあるのです。
テスラは“機械好き”や“ガジェット好き”にはたまらない魅力を持っていますが、日常使いの中で自然に直感的に操作したいという人には、合わない可能性もあります。
結局のところ、「カッコよさ」や「最新感」に惹かれて購入したはずが、毎日の運転の中で**「ちょっとした操作のたびにストレスが溜まる」→「やっぱりやめとけばよかった」という後悔**につながる。
そんなケースも、決して少なくないのです。
嫌われる理由とは?SNSでのアンチや偏見の現実
テスラが「やめとけ」と言われる理由には、車の性能や品質といった“ハード面”だけでなく、世間のイメージやSNS上での偏見、アンチの存在といった“ソフトな要因”も大きく関わっています。つまり、実際に乗るかどうかに関係なく、「テスラ=嫌われがちな存在」とされてしまう風潮があるのです。
まず目立つのが、SNSや掲示板で見かける**「テスラ乗り=意識高い系」というラベリングです。
これは、「EVはエコだ」「テクノロジーで未来を変える」といった理念に共感してテスラを選ぶユーザーが多いことから生まれたイメージで、実際には真面目にテスラを支持しているだけでも、“マウントを取ってくる”“自分が正義”と見られやすい**という不思議な構図があります。
さらに、一部のオーナーがSNSで自慢げに「テスラのない生活はもう考えられない」といった発信をすると、これが火に油を注ぐ形でアンチを生み出してしまうこともあります。
このような発言が**“乗ってない人を見下している”という風に受け取られ、結果としてテスラ全体が「嫌な人が乗る車」**という誤解に繋がってしまうのです。
また、日本国内ではまだEVインフラが十分に整っていない地域も多く、「充電で渋滞を作る」「エンジン車を見下す」などのトラブル報告がX(旧Twitter)やYouTubeのコメント欄で頻繁に話題になります。
これにより、「テスラ乗ってる人ってマナー悪いよね」といったネガティブな印象が広がりやすい状況になっています。
もちろん、すべてのオーナーがそういう人ではありません。実際は静かに愛車を楽しんでいるユーザーもたくさんいます。
しかし、テスラというブランド自体が非常に話題性が高く、“イーロン・マスク”というカリスマを抱えていることで、何かと注目を浴びやすく、良くも悪くも“目立つ存在”であることは間違いありません。
さらに、テスラに否定的な人の中には「電気自動車=将来の主流になるのが気に入らない」「アメリカ企業が自動車業界のルールを変えるのが不快」というように、イデオロギー的にアンチ化している層も存在します。
これはもはや“車の話”というより、“社会の変化に対する反発”に近くなっており、ユーザーが悪くなくても無用な敵意にさらされるリスクがあるのです。
そしてもう一つ忘れてはいけないのが、「見栄で買ってると思われる」問題です。
たとえば、モデルYのパフォーマンスやモデルSなどを所有していると、「ああ、あれ見せびらかし目的だよね」といった妬みや偏見が向けられるケースもあります。
こうした外野の声にストレスを感じやすい人にとっては、所有すること自体が精神的な負担になる可能性もあるでしょう。
つまり、テスラが「やめとけ」と言われる背景には、車そのものの実力以外に、“社会的な視線”が複雑に絡んでいるのです。
だからこそ、テスラを選ぶ際は「車としての性能や魅力」だけでなく、「周囲の目をどう受け止めるか」という心の準備も含めて判断することが大切です。
テスラを買って後悔しないために|購入前に考えるべき5つの視点

ラグジュアリードリームイメージ画像
ここまで「テスラはやめとけ」と言われる理由を見てきたように、車としての完成度や購入後のサポート体制、さらには社会的なイメージまで、テスラにはさまざまな“クセ”があります。
とはいえ、それでもテスラが世界中で支持され、熱狂的なファンを獲得し続けているのも事実です。
つまり、「やめとけ」と言われるかどうかは、その人の価値観や使い方次第。だからこそ、これからテスラを検討している方にとって重要なのは、「自分は本当にテスラに向いているのか?」を見極めることです。
後悔しないためには、「どんな人がテスラに合うのか?」「どんな落とし穴に気をつけるべきか?」を事前に知っておくことが欠かせません。
ここからは、テスラに向いている人・向いていない人の特徴を踏まえながら、購入前に考えておきたい5つの視点をご紹介していきます。
・テスラはどんな人に向いている?失敗しないための判断軸
→ 革新性を楽しめる人、整備への柔軟性がある人など「向いてる人」の特徴。
・内装や質感に何を求める?価格と期待のギャップを理解
→ 欧州車のようなラグジュアリーを求める人が後悔する理由とは?
・テスラの維持費とコスト感覚|安いと思ったら意外な落とし穴も
→ 充電・保険・修理費・部品代など、思わぬコストが後悔につながるパターンを整理。
・モデル3・モデルY・S・X…どれを選ぶべきか?後悔しにくい選び方
→ モデルごとの特徴と、後悔しやすい選び方(「とりあえず安いからモデル3」など)
・最終判断は「憧れ」だけで決めない|“比較と覚悟”のバランス
→ 他車との比較と、テスラを選ぶうえで必要な覚悟・心構えの整理。
テスラはどんな人に向いている?失敗しないための判断軸
テスラという車は、万人受けするタイプではありません。けれども、その独自性を理解したうえで選ぶのであれば、これ以上ない満足感を得られる車でもあります。
そこでまず考えたいのが、「どんな人がテスラに向いているのか?」という点です。
結論から言えば、“革新を楽しめる人” “柔軟性のある人” “自己判断ができる人”。この3つの資質を持っている人ほど、テスラとの相性は抜群です。
たとえば、定期的なアップデートで機能が進化することをワクワクと捉えられる人。内装のミニマルさに「余計なものがなくていい」と感じられる人。さらには「ちょっとくらいトラブルがあっても、自分で調べて解決するのが楽しい」と思えるような人。
このようなタイプの方は、テスラに乗ることで日々の生活に**“刺激”や“発見”**を得ることができます。
逆に言えば、「クルマは静かに、快適に、トラブルなく使えることが当たり前」と考える人には、テスラはストレスのもとになる可能性が高いです。
ユーザーサポートに即応性を求めたり、ディーラーの丁寧な対応に慣れている人にとっては、テスラの“効率重視・自己完結型”の運営体制は物足りなく感じるでしょう。
さらに、「車はステータスであり、周囲からの評価も大切」と考える人にとっては、SNSなどで向けられる偏見やアンチの存在も、精神的な負担になるかもしれません。
また、機械に対する苦手意識がある人や、高齢者の方には操作系が合わないケースも多いです。
実際に筆者の知人で、70代の方がモデル3に乗り換えたものの、タッチパネル操作に慣れず1年で国産車に戻ったというケースもありました。
つまり、テスラを買って後悔しないためには、「自分のスタンスとクルマの性格が一致しているか?」をじっくり考えることが重要です。
単に見た目や評判、話題性で選ぶのではなく、“どんな毎日をこの車と過ごしたいか”という視点で判断することが、後悔のない選択へとつながるのです。
内装や質感に何を求める?価格と期待のギャップを理解
テスラを初めて購入しようとする人の多くは、「価格帯に見合った高級感」や「未来的で洗練された空間」を期待しています。実際、モデル3やモデルYでも500〜800万円、モデルSやXでは1,000万円を超える価格設定。これだけの金額を出せば、当然ながら「上質な内装」「快適な居住性」「ラグジュアリーな雰囲気」を求めたくなるのが自然です。
しかし、ここでギャップが生まれます。
テスラの内装は、あくまで「シンプル・合理的・最小限」を追求した設計であり、伝統的な高級車に見られるような木目パネルや手縫いステッチ、メタル加飾といった“装飾的な豪華さ”とは真逆の方向性を持っています。
たとえば、モデル3に乗ったときに「高級車らしい香りや重厚感がない」と感じたという声は多く、シート素材やインパネの質感について「チープ」「安っぽい」といったレビューも少なくありません。
さらに、シートのホールド感やクッション性についても、「長距離だと疲れる」「欧州車に比べて出来が甘い」と評価するユーザーもいます。
これは必ずしもテスラの“手抜き”というわけではなく、彼らなりの合理性と設計思想に基づいた選択です。イーロン・マスク率いるテスラは「車内をできる限りシンプルにし、すべてをソフトウェアで統合する」というビジョンを掲げており、そこには「過剰な装飾は無駄」という考え方が根底にあります。
とはいえ、それを知らずに購入してしまうと、「えっ?この価格でこれ?」という印象を受け、購入後の満足度を大きく下げてしまう可能性があります。
また、比較対象がドイツ車(メルセデス・BMW・アウディ)である場合、このギャップはさらに大きくなります。
筆者の知人でEクラスからモデルYに乗り換えた方は、「走りは面白いけど、車内に乗り込むたびに“ダウングレードした感”が拭えない」と率直に語っていました。
一方で、「内装なんてどうでもいい、走りとテクノロジーが全て」と割り切れる人や、ミニマルな空間に価値を感じる人にとっては、テスラの内装はむしろ“潔くて好印象”となる場合もあります。
つまり、テスラに「質感」や「雰囲気的なラグジュアリー」を期待するか、それとも「機能」と「未来感」を求めるかによって、その評価は大きく分かれるのです。
購入前には必ず実車を見て、内装を触り、乗り込み、「この空間で毎日過ごせるか?」を確認することをおすすめします。
カタログやSNSの写真だけでは伝わらない“実際の肌感”を体験しておくことが、後悔しないためには欠かせない判断材料になるでしょう。
テスラの維持費とコスト感覚|安いと思ったら意外な落とし穴も
「EVは維持費が安い」——これはテスラを検討する人の多くが抱くイメージです。
確かに、エンジンオイルの交換やタイミングベルトのメンテナンスといった内燃機関特有の整備が不要で、燃料代も電気の方が安く済む傾向にあります。
しかし実際には、想像以上に“見えないコスト”がかかるというのが現実で、ここを理解していないと購入後に後悔することになります。
まずは充電にかかるコスト。自宅にEV用の普通充電器(ウォールコネクター)を設置する場合、工事費用込みでおよそ15〜30万円程度かかります。
マンションや賃貸物件に住んでいる方にとってはそもそも設置できない場合もあり、その場合は近くの急速充電器やスーパーチャージャーを使う必要がありますが、この“外部充電依存”が意外と高くつくのです。
たとえば、テスラのスーパーチャージャーは2024年現在、1kWhあたり約60円前後。満充電に必要な電力が約70〜80kWhとすると、1回の充電で約4,000〜5,000円前後になることもあり、これは燃費の良いハイブリッド車と大差ない、あるいはそれ以上になるケースもあります。
次に保険料。
テスラは事故時の修理費が高額になることが多く、車両保険付きの任意保険料が高くなりやすい傾向にあります。
とくに車両価格が800万〜1000万円を超えるモデルSやXでは、保険料が年15万〜20万円以上になることも珍しくありません。
また、タイヤやブレーキといった消耗品にも注意が必要です。
モデル3やYのパフォーマンスモデルに装着されている20インチ以上のタイヤは、1本あたり5〜6万円が相場で、4本交換すれば20万円超え。さらに重量のあるEVはタイヤの摩耗が早く、2万〜3万kmごとに交換が必要になる場合もあるのです。
加えて、万が一の修理費も高額です。
テスラの修理は専用設備と技術を持つ認定工場でしか対応できないケースが多く、バンパーやセンサーまわりを軽くぶつけただけでも修理費が50万円超えという話もよく聞かれます。部品の取り寄せに時間がかかるため、修理期間中に代車が出ないと生活にも支障が出てしまいます。
さらに、テスラはアップデートで機能が追加される一方で、一部の機能は有料オプションでの解放が必要です。たとえばFSD(完全自動運転)機能は、2024年時点でフル装備にすると約100万円以上という価格設定。これを「標準装備だと思ってた」と誤解して後悔するケースもあるため要注意です。
このように、表面上は“燃料代が安くてエコ”という印象があるテスラですが、トータルで見ると意外にお金がかかる車であることをしっかり認識しておく必要があります。
購入前には、単にガソリン代の節約分だけで判断するのではなく、ライフスタイルに合った維持のしやすさまで含めて検討することが、後悔を防ぐためのカギとなるでしょう。
モデル3・モデルY・S・X…どれを選ぶべきか?後悔しにくい選び方
「テスラに乗ってみたいけど、どのモデルを選べばいいか迷う…」
これは購入を考えている人が必ず通る悩みです。ラインナップはモデル3、Y、S、Xと幅広く、それぞれに価格・サイズ・性能・使い勝手が大きく異なります。
間違った選び方をすると、「こんなはずじゃなかった」と後悔することにもなりかねません。
まず、もっとも普及しているのがモデル3。
セダン型で価格もテスラの中では比較的抑えめ。日本の道路事情にもマッチしやすく、エントリーモデルとしては優れています。ただし後部座席の天井が低く、大人4人で長距離移動するにはやや窮屈。トランクもセダン型特有の開口部が狭く、荷物の積み下ろしがやや不便という声もあります。
一方で近年人気を急上昇させているのがモデルY。
モデル3のSUV版とも言えるこの車種は、広い室内空間と実用性の高さが魅力です。後席やラゲッジスペースもゆとりがあり、ファミリー層やアウトドア派にぴったり。価格差もモデル3とそこまで大きくないため、日常使いを重視する人にはこちらがオススメです。ただし、SUVとはいえ乗り心地はやや硬めなので、柔らかい足回りを好む人は試乗必須です。
上位モデルとなるのがモデルSとモデルX。
モデルSはハイパフォーマンスセダンで、ロングレンジモデルなら一充電で600km超を実現。内装の質感も上位グレードらしく高く、テスラらしい先進性も随所に光ります。しかし価格は1,000万円超え。車両保険料や修理費も跳ね上がるため、維持コストの覚悟が必要です。
モデルXはガルウィングドアが象徴的な大型SUV。最大7人乗りも可能で、荷物もたくさん積める優れた実用車です。ただしそのサイズから日本の都市部では取り回しに苦労する場面も多く、狭い道や立体駐車場では持て余す可能性も。
また、修理や部品交換となると、特殊な構造ゆえに時間もお金もかかる点には要注意です。
後悔しやすいパターンとしては、「価格重視でモデル3を選んだけれど、荷物が積めず使いにくい」とか、「かっこよさだけでモデルXを選んだけど、大きすぎて乗るたびに気疲れする」といったケースです。
こうした後悔を防ぐには、自分のライフスタイルと車の特性が合っているかを冷静に見極めることが不可欠です。
また、モデルごとにリセールバリューも異なります。現在(2024年時点)で最もリセールが安定しているのはモデルY。普及台数が増えており中古需要も高いため、数年後の売却を見据えた選択にも向いています。
結論として、「価格だけ」「見た目だけ」で選ばないことが何より大事。
それぞれのモデルの強み・弱みを把握した上で、自分が日常的にどんな使い方をするのかを基準に選べば、きっと後悔のないテスラ選びができるはずです。
最終判断は「憧れ」だけで決めない|“比較と覚悟”のバランス
テスラに興味を持つ人の多くが、最初に感じるのは「憧れ」や「未来感」です。
スマートで無駄のないデザイン、EVならではの加速性能、そしてイーロン・マスクというカリスマ的なブランド力。
このワクワクは、他のどんな車にもない魅力だと思います。実際、筆者自身も初めてモデル3に乗ったときは「これが次世代の車か…」と感動すら覚えました。
しかし、車は“夢”だけでなく、“道具”であり“現実”でもあります。
毎日乗るものだからこそ、「実用性」「費用」「サポート」「ライフスタイルとの相性」など、冷静な判断が必要です。
テスラを買った人の中には、「SNSでの注目度が高い」「周囲に“すごいね”と言われた」という理由で選んだ結果、数ヶ月後に「思ったより使いにくい」「メンテナンスが大変」といって手放す人もいます。
また、購入直後は満足していても、アップデートで仕様が変わって戸惑う、パーツが入らず修理が長引く、充電が不便…と、後からジワジワと不満が積もってくるケースもあるのです。
では、後悔しないためにはどうすれば良いのか?
結論としては、“比較”と“覚悟”を持って選ぶこと。
比較とは、他の車との違いをしっかり把握して、自分の価値観と照らし合わせることです。
たとえば、「静かでスマートな走りが欲しいのか?」「高級感のある質感を大事にしたいのか?」「家族で荷物をたくさん積みたいのか?」など、自分のライフスタイルを軸にして、本当にテスラが合うのかを他の選択肢とも見比べてみましょう。
そして覚悟とは、テスラ特有のクセや欠点を理解した上で、それも“含めて楽しめるか”という気持ちです。
アフターサービスが日本車並みでないこと、充電に少し不便さがあること、内装がシンプルすぎること。
こういった部分に対して「それでもテスラに乗りたい」「未来を感じられるからOK」と思えるなら、あなたはきっとテスラに向いているはずです。
要するに、「好きだから買う」は悪くない。
でも、「好きなだけで買う」と、あとで苦しくなる。
それがテスラという車なのだと思います。
未来を体験できる車、それがテスラ。
でもその未来には、“ちょっとした試練”や“他の車とは違う常識”もセットでついてくる。
そのことを知ったうえで、自分に合った選択をすることが、後悔しないテスラとの付き合い方なのです。
まとめ:テスラは万人向けではない。“尖った選択”に納得できるかが後悔しない鍵
テスラは間違いなく、これまでの車とは一線を画す存在です。
走行性能の高さ、ソフトウェアアップデートによる進化、そして独自のブランド性。どれをとっても、従来の自動車メーカーが持っていなかった要素を持ち合わせています。
ただし、その一方で「品質が荒い」「アフターサービスが不安定」「充電インフラに課題がある」といった欠点もはっきりしており、誰にとっても“完璧なクルマ”とは言い切れません。
事実、テスラを購入したものの、「思ったのと違った」「やめとけばよかった」と後悔している人も一定数存在します。
では、テスラを選んで後悔しないために大事なことは何か?
それは、“自分が何に価値を置くか”をはっきりさせることです。
例えば、「EVとしての先進性を日常に取り入れたい」「アップデートで進化する楽しさを味わいたい」「車というよりガジェットとして使いこなしたい」——こうした価値観を持っている人にとって、テスラはきっと最高の選択になるでしょう。
逆に、「静かに壊れず走ってくれればそれでいい」「ラグジュアリーな内装がないと満足できない」「何かあったときにすぐに対応してくれるディーラーが必要」
こうした考えが強い場合は、国産高級車やドイツ車の方が合っているかもしれません。
大切なのは、「テスラは未来のクルマだから」「周りが乗っているから」といった雰囲気や憧れだけで決めないこと。
テスラは“尖った選択”です。性能も体験も革新的ですが、そのぶん従来の車と比べて“慣れ”や“許容”を必要とします。
その尖りに納得できるかどうか——そこが、後悔するかしないかの分かれ道になります。
最後に改めてお伝えしたいのは、テスラは素晴らしい車です。
ただし、誰にとってもベストな車ではありません。
だからこそ、自分の価値観とライフスタイルを見つめ直し、「それでもこの車に乗りたい」と思えたとき、テスラはきっと、あなただけの“特別な一台”になるはずです。