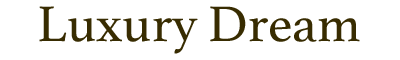BYD公式画像引用
「BYDって、意外と売れてないよね?」
そう感じている人は、実際に多いのではないでしょうか。僕自身も、BYDという名前を初めて耳にしたときは「なんで中国の自動車メーカーが日本で?」と半信半疑でした。でも調べてみると、世界的にはテスラに並ぶほどのEVメーカーで、技術力も実績もある。なのに、なぜ日本ではBYDが売れないのか――そこに大きなギャップを感じたんです。
EVの流れが世界中で加速している今、BYDはその中心にいる存在です。特に中国本土では、タクシーから一般車まで広く普及しており、「EV=BYD」と言っても過言ではないほど。ただ、日本市場においては思ったほど普及が進んでいないのが現状。CMや試乗イベントは積極的に行われているのに、「実際に乗ってる人を見かけない」「ディーラーが少ない」「なんか信用できない」といった声を聞くたびに、BYD 売れない理由を考えざるを得ませんでした。
僕の周りにも車好きや業界関係者が多くいますが、彼らの多くもBYDに対しては「気になるけど手は出さない」というスタンス。実際に試乗してみて「悪くないじゃん」と感じる人もいるのに、購入には踏み切らない。そこには、スペックや価格では測れない“空気”のようなものが存在しているように思います。
つまり、BYDが売れない理由は単に「車が悪い」からではなく、日本独特の市場構造や文化的な背景、消費者の心理的な壁にあるというのが、僕の正直な見解です。
この記事では、
・日本でBYDが売れない理由の裏にある“見えない壁”
・技術や価格だけでは測れない日本市場の特殊性
・実際に乗った人・試した人のリアルな声
・そして、今後BYDが日本で選ばれる可能性
これらのポイントをもとに、車好きとしての体験や考察も交えながら、他では読めないリアルな視点で深掘りしていきます。
検索してこの記事にたどり着いたあなたに、「なるほど、そういう理由だったのか」と思ってもらえるような内容をお届けします。
BYD公式動画引用
BYD 売れない理由は?日本市場で苦戦する“見えない壁”とは
BYD(比亜迪/ビーワイディー)は、今や中国国内のみならず世界中でEV(電気自動車)を展開し、2023年にはテスラの年間販売台数を超えたとも言われています。なのに、日本では「BYDって何?」という人がまだ大半。テレビCMやYouTube広告、さらには長澤まさみさんの起用など、プロモーションにもかなり力を入れているにも関わらず、日本の街中ではBYDのクルマを見かける機会は非常に少ないのが現状です。
このセクションでは、「なぜBYDは売れないのか?」という検索ユーザーの疑問に対し、情報と体験をもとに、日本市場における“見えない壁”をわかりやすく解き明かしていきます。
・そもそもBYDはどんな会社?世界で売れて日本で売れない不思議
→ 世界的な実績を紹介しつつ、日本市場とのギャップを提示。
・ディーラーが少なすぎる?販売網の弱さが最大のネック
→ 実際に探してみて「近くにない」と感じた経験と、ユーザーの足が遠のく理由を語る。
・中国車というだけで避けられる?日本人の根強いイメージと不安感
→ 「中国=安かろう悪かろう」のイメージが、なかなか消えない現実。
・日本人が“ブランド”に求める安心感とBYDの課題
→ トヨタやホンダの「見えない信頼」に勝てない理由を文化的に考察。
・実は車は良い?それでも売れないリアルな理由とは
→ 実際に乗って感じた性能の高さと、でも買わない“もったいない現象”について。
そもそもBYDはどんな会社?世界で売れて日本で売れない不思議
BYDは1995年に中国・深センで創業された企業で、当初はスマートフォンなどに使われるリチウムイオン電池の製造メーカーでした。2003年に自動車業界に参入し、現在では世界屈指のEV(電気自動車)メーカーへと成長を遂げています。社名の「BYD」は「Build Your Dreams(夢をカタチに)」の略で、企業としてのスローガンにもなっています。
驚くべきは、その販売台数のスケール感です。2023年の世界EV販売台数は約302万台。これはテスラの約180万台を大きく上回っており(※参考:BYD公式プレスリリース)、世界的にはテスラと並ぶ、あるいは凌駕するEVブランドとしての地位を確立しています。
その勢いは中国国内だけでなく、欧州、中東、オーストラリア、東南アジア、南米などにも広がっており、国によっては公共交通機関のEVバスの標準車両としてBYDが採用されている地域もあります。事実、筆者の知人が住むタイやシンガポールでは、BYDのタクシーや一般車が当たり前のように街中を走っているとのこと。現地ではすでに「新しい世代のスタンダード」として認識されているわけです。
これだけの規模と実績があるのに、なぜ日本ではこれほどまでに存在感が薄いのか――。BYDを調べれば調べるほど、そのギャップが不思議に思えてきます。
その理由を考えてみると、日本市場には**“クルマの良し悪し”だけでは測れない、文化的・心理的な壁**があることに気づきました。性能が良い、デザインが先進的、価格も魅力的。それでも売れない。
これは「商品」ではなく「市場の特性」が大きく関係しているというのが、僕なりの結論です。
ディーラーが少なすぎる?販売網の弱さが最大のネック
自動車を買うとき、多くの人はまず「どこで買えるか?」を気にすると思います。僕自身、BYDに興味を持ってから、すぐに公式サイトで販売店を検索してみました。結果、最寄りの店舗まで車で1時間以上…。この時点で「ちょっと面倒だな」と感じてしまったのが正直なところです。
現時点でBYDが日本国内に展開している正規ディーラーは全国で40店舗前後(2025年3月時点)にとどまっています。これは、トヨタや日産のように数千店舗を持つ国内大手メーカーと比べて圧倒的に少ない数字です。
この販売網の弱さが、BYDの“売れない理由”として非常に大きなネックになっていると感じます。というのも、車というのはカタログやネットの情報だけでは分からない部分が多く、実際に見て、触れて、試乗して、営業担当と話して…という「リアルな接点」がとても重要な買い物だからです。
たとえば、ディーラーが近くにあれば、「ちょっと通りがかりに見てみよう」「買う予定はないけど試乗だけでも」というライト層の導線が生まれます。しかし、今のBYDはそれができない。
これは「存在を知ってもらうためのタッチポイント」が少なすぎるということでもあります。
また、購入後のメンテナンス・保証・トラブル対応の不安も大きな課題です。近所にディーラーがなければ、「修理のときどうするの?」「部品取り寄せに時間がかかるんじゃ?」という心配が出てきます。僕自身も、クルマは日常的に使うものなので、アフターサポートの充実度は購入検討時の大きな要素になります。
実際、僕の車仲間の中には「BYDの車は気になるけど、近くに店舗がないから諦めた」という人が複数います。どんなに商品が優れていても、それを“手に取りやすく”してくれる流通網がなければ、売れるものも売れません。
つまり、BYDが売れない理由のひとつは**「モノが悪い」ではなく、「売るための仕組みが足りていない」**ということ。この差をどう埋めていくかが、今後の鍵になるでしょう。
中国車というだけで避けられる?日本人の根強いイメージと不安感
「中国車って大丈夫なの?」
この言葉、僕自身、何度も耳にしてきました。実際にBYDに興味を持っている人でも、この“不安感”が最後の一歩を踏みとどまらせているケースは非常に多いです。しかもこの不安の正体は、はっきりと「ココがダメだから」というわけではなく、漠然とした印象やイメージで語られることがほとんどです。
では、なぜ私たちは中国製の車にこうも警戒心を抱いてしまうのでしょうか?
ひとつは、過去に流通していた中国製品に対する「安かろう悪かろう」の印象が強く残っているからだと思います。たとえば、安価なスマホや家電製品が数年で壊れたり、模倣品が問題になったりした時期がありました。僕の周りでも「中国製=耐久性が低い」「サポートが不安」というイメージを持っている人が少なくありません。
しかし、実際には今の中国製品は当時とは大きく異なっています。BYDに限らず、HuaweiやXiaomiなど、スマホ業界でもグローバルに活躍する中国メーカーが台頭していますし、自動車においても技術・デザイン・品質の面で世界水準に到達しているのは事実です。
BYDの「ブレードバッテリー」は発火リスクの低減に優れた構造を採用しており、安全性も高いと評価されています。2022年にはヨーロッパの安全性評価機関「Euro NCAP」で、BYD ATTO 3が最高評価の5つ星を獲得しました(※公式結果あり)。これはトヨタやホンダの新型車と同等の評価です。
それでも「それは分かっているけど、やっぱり中国っていうのが引っかかるんだよなぁ…」という感情が先に来てしまう。これは性能やデータではなく、感情の問題です。そして日本人は特に、信頼やブランドに対して“保守的”な気質が強いと僕は思います。
周囲が乗っていない車、周囲が知らないメーカーに飛び込むには、それなりの“勇気”が必要です。これは決して悪いことではありません。ですが、それが結果的に新しい価値を遠ざけていることにもなりかねない。
中国車というだけで避けることが、どれだけもったいないことか――それに気づける人が今後どれだけ増えるかが、BYDの未来を左右する気がします。
日本人が“ブランド”に求める安心感とBYDの課題
僕たち日本人は「ブランド=信頼の証」と捉える傾向がとても強い民族です。たとえば、家電を買うときに「パナソニックだから安心」「ソニーなら大丈夫」と感じる人、多いですよね?
クルマに関してもそれは同じで、「トヨタ」「ホンダ」「日産」といった国産メーカーには、**“性能”を超えた安心感=ブランド信頼”**が根付いています。
この“見えない信頼”が、BYDにはまだ圧倒的に足りない。
たとえ車そのものの性能がよくても、「初めて聞いた名前」「周囲に持っている人がいない」「情報が少ない」といった不安材料があると、購入への心理的ハードルは一気に高まります。
これは僕自身がBYD ATTO 3を見たときに感じたことでもあります。「クルマ自体は悪くない。むしろ良い。でも、本当にこのメーカーを信用していいのか?」と、心の中で慎重になる自分がいました。
さらに、日本では“周囲と同じものを選ぶ安心感”が大切にされる文化があります。つまり、「他の人も使っているから安心」という集団意識が、車選びにも大きく影響しているんです。
BYDには、まだ「周囲の人が乗っている」という事例が少なく、ネット上のレビューも国産車ほど豊富ではない。だからこそ、「実際どうなの?」という疑問が拭えず、買うまでに至らない人が多いんだと思います。
この点を克服するためには、安心を感じさせる情報発信と接点づくりが今後重要になってくるでしょう。たとえば試乗会の充実、納車後のサポート実例紹介、購入者の声の発信など。実際にBYDに乗っている人の“リアルな体験”が少しずつ世の中に広まれば、この“見えない不安”は少しずつ和らいでいくはずです。
実は車は良い?それでも売れないリアルな理由とは
僕が初めてBYD ATTO 3に乗ったとき、正直「これは売れるんじゃないか」と思ったほどです。走りはスムーズ、内装の質感も高く、装備も充実している。それでいて価格は補助金込みで300万円台。
国産EVと比較しても、性能・価格ともに魅力的でした。
でも、その後いろんな人に「BYDどうだった?」と聞かれても、「良かったよ」と答える一方で、「でも…」と続けてしまう自分がいたんです。
その「でも」の正体は、やはり**“空気感”の壁**でした。
これは数字やスペックでは説明しきれない、日本市場特有の“なんとなく不安”という空気。
購入後のサポートは?
リセールバリューは?
周りの目は?
SNSでの評判は?
どれもハッキリした「欠点」ではないけれど、複合的な不安が購入の足を止めている。
これは僕の車仲間にも当てはまります。ある友人は、ATTO 3に試乗して「めちゃくちゃ良かった」と言いながら、最終的には国産EVを選びました。理由を聞くと、「もし何かあったときに対応が不安」「みんながまだ知らないメーカーはちょっと…」とのこと。
つまり、「良い車だから売れるわけじゃない」のが現実なんです。
クルマ選びには感情、評判、信頼、そして“安心できる空気”が必要。BYDが売れない理由の本質は、車そのものではなく、日本人の“買うための安心条件”がまだ整っていないことにあると僕は考えています。
BYD 売れない理由の先にある可能性とこれから選ばれる未来
今の日本では「BYD=売れていない」という印象が根強いのは事実です。
でも、僕はそれを単なる“失敗”とは捉えていません。むしろ、まだ始まったばかりのブランドが、日本独自の市場に適応しきれていないだけ。そして、それは時間と戦略次第でいくらでも覆せると感じています。
実際にBYDの車に触れてみて、「あれ?思ってたのと違う」「普通にいいじゃん」という声を何度も耳にしてきました。そうしたギャップの積み重ねが、これからの可能性を大きく広げていくはずです。
このセクションでは、「今は売れていない」からこそ見えてくるBYDの強みやポテンシャル、そしてこれから日本で選ばれる未来について、体験談や市場動向を交えてお伝えしていきます。
・試乗して初めて分かる魅力と変わる印象のギャップ
→ 自分や周囲の「乗ってみたら全然アリ」という感想の紹介。
・EVシフトの波とBYDのポジショニングの強み
→ 補助金、燃費、環境意識の高まりで「買う理由」が整いつつある話。
・今後の販売戦略次第で一気に火がつく可能性も?
→ 充実したディーラー展開やサポート体制が整えば広がると予想。
・Z世代・若者はむしろBYDに向いている?価値観の変化に注目
→ ブランドより中身で選ぶ世代が、BYDの時代をつくる可能性。
・先入観を捨てたとき、BYDは“普通に選ばれるクルマ”になる
→ 乗ってみて感じたリアルな価値と、これから「当たり前になる未来」の兆し。
試乗して初めて分かる魅力と変わる印象のギャップ
BYDに対する印象がガラッと変わる瞬間――それは、実際にクルマに乗ってみたときだと断言できます。
僕自身がそうでした。ATTO 3に初めて試乗したとき、それまで抱いていた「中国車=チープで信頼できない」というイメージが、スーッと消えていくのを感じました。
電動シートに腰を下ろし、静かな加速、滑らかなハンドリング、そして内装の質感。あまりに“普通に良くて”、逆に戸惑ったほどです。
そしてこの感覚、実は僕だけではなく、周囲の知人たちにも共通していたんです。
ある友人(30代・輸入車好き)は、「正直、なめてた。でもこれ、普通にアリだよね」と驚いていました。
別の友人(50代・EVに懐疑的)は、「もっと粗があると思ってたけど、これなら国産EVより全然いいかも」と納得していました。
このように、「試乗して初めて分かる良さ」がBYDには確実にあります。裏を返せば、乗ってもらえさえすれば、“売れない理由”の多くはその場で消える可能性があるということです。
これはまさに、“情報のギャップ”と“体験の不足”が作っている壁。
BYDにとって必要なのは、大規模な広告よりも、「まず乗ってもらう」「触れてもらう」機会をどれだけ増やせるかだと感じています。
EVシフトの波とBYDのポジショニングの強み
世界的に見ても、今はまさにEVシフトの真っ只中。
日本でも2035年までにガソリン車の新車販売をゼロにするという国の方針が打ち出されており、自動車メーカー各社はEVのラインアップを加速させています。
ただし、EVには価格の壁、充電環境の壁、選択肢の少なさなど、課題も多い。そんな中で、BYDの存在は“ちょうどいいポジション”にあると僕は思っています。
例えばATTO 3。
補助金を適用すれば300万円台で購入可能で、国産EVよりも装備は豪華、デザインも先進的。加えて、EV専業メーカーとして長年蓄積してきたバッテリー技術や航続距離の信頼性も高く、「コスパ」と「実用性」のバランスがとれているのが大きな強みです。
また、BYDは「自社でバッテリーも車体も作れる」という、世界でも数少ない**“垂直統合型メーカー”**。これができるからこそ、価格を抑えつつ品質を安定させることが可能になっているんです。
EVにシフトしていくこれからの時代、「なるべく費用を抑えつつ、信頼できるEVに乗りたい」というニーズは必ず増えていくはず。
そのとき、BYDのポジションはまさに“最初の1台にちょうどいいEV”として受け入れられる土壌があると、僕は感じています。
今後の販売戦略次第で一気に火がつく可能性も?
今は「売れていない」と言われているBYDですが、裏を返せば、まだスタート地点に立ったばかり。
むしろ、これからの戦略次第で一気に火がつく可能性を秘めていると僕は考えています。
特に重要なのは、ディーラー網の拡充とユーザーサポート体制の構築です。
現状では都市部に限られた数のショールームしか存在せず、地方在住の人にとっては現物を見ることすら難しい。
しかし、もしこれが全国規模で整ってくれば、興味を持つユーザーに“触れる機会”を提供でき、試乗や購入までの導線が大きく変わってくるでしょう。
また、今後はサブスクリプションやカーリースなど、“購入前提ではないEVの使い方”も広がっていくと予想されます。
その中で、BYDのような新興ブランドは、柔軟なプラン設定やアフターサービスの安心感を打ち出すことで、一気に注目される可能性があるんです。
トヨタやホンダのような“大手”と同じやり方ではなく、BYDならではの戦略で“逆転”できる余地は十分ある――それが、今の「売れていない」からこそ見えてくるチャンスだと思います。
Z世代・若者はむしろBYDに向いている?価値観の変化に注目
「若者の車離れ」と言われるようになって久しいですが、それは単に「車に興味がない」のではなく、“価値観が変わっている”ことの表れだと僕は思っています。
Z世代やミレニアル世代の多くは、クルマを「ステータス」ではなく、「移動手段+個性の表現」として捉えている傾向が強いです。そして何より、彼らの多くが“中身重視”の判断基準を持っていて、ブランドに過剰な信仰を持たない。
つまり、「トヨタだから安心」「ベンツだからすごい」というような“ブランドバイアス”よりも、
「機能はどうか?」「価格に対する価値はあるか?」「人と被らないか?」という視点を持ってクルマを選ぶ傾向があるわけです。
この視点で見たとき、BYDというブランドは若者世代にとって実は非常に相性がいいんじゃないかと僕は感じています。
・個性的なデザイン(内外装ともに先進的)
・スマホのようなインターフェース(タッチ操作のダッシュボードなど)
・360度カメラやスマートキー、電動シートなどの豊富な装備
・補助金込みで300万円台〜という手の届く価格帯
・そしてまだ「乗ってる人が少ない」という新鮮さ
これらは、Z世代が重視する「自分らしい選択」「新しい体験」「無駄のない買い物」という感覚にしっかり合致していると思います。
実際、僕の後輩(20代後半)はBYD ATTO 3に強い関心を持っていて、「国産車はデザインが無難すぎて面白くない」と言っていました。
彼にとっては、BYDのような“ちょっと尖った存在”がむしろ魅力的だったんです。
今後、日本でもEVが当たり前になっていく中で、「初めて買うEV」としてBYDを選ぶ若者は確実に増えていくと思います。
むしろ、彼らのような“ブランドにとらわれないフラットな感覚”を持った層こそ、BYDが本当に価値を発揮するターゲット層なのかもしれません。
先入観を捨てたとき、BYDは“普通に選ばれるクルマ”になる
「中国車=安っぽい」「壊れやすい」「信用できない」
このイメージ、正直なところ、僕も最初は完全に持っていました。でも、それは乗ってみることで一気に崩れました。
ATTO 3に試乗したとき、まず驚いたのは走りのスムーズさ。そしてインテリアの未来感。
エアコンの吹き出し口がギターの弦のようなデザインになっていたり、ディスプレイが回転して縦にも横にも使えたり――正直、ワクワクしました。
「これが中国車?」と何度も思ったほどです。
でも面白いのは、そう感じたのが僕だけじゃなかったこと。
周囲にBYDを紹介して試乗してもらうと、ほとんどの人が「え?意外といい」「全然アリだね」と反応してくれる。中には「ちょっと考えてみようかな」と言い出す人まで。
このとき僕が感じたのは、「BYDは“乗れば分かるクルマ”」だということです。
だからこそ、先入観を持ったままだと絶対に気づけない魅力が、そこにはある。
日本人はどうしても「みんなが乗っている=安心」という考え方をしがちです。でも、その感覚から一歩外れて、自分の目と感覚で判断できる人が増えれば、BYDは“普通に選ばれるクルマ”になる日が必ず来ると思います。
むしろ、今は「まだ周囲が乗っていない=先取りできる」タイミング。
そういう意味では、BYDにいち早く気づいた人は“目利き”とも言えるでしょう。
これからBYDの販売網が広がり、購入者の声が増えていけば、先入観は自然と消えていきます。
そして気がつけば、街中でBYDのエンブレムを見かけることが“当たり前”になっていくはずです。
まとめ:BYDが「売れないクルマ」から「選ばれる存在」へ変わる日は近い
この記事では、「BYD 売れない理由に迫る|なぜ中国EVは日本で選ばれにくいのか?」というテーマをもとに、
● なぜ世界で売れているのに日本では売れないのか?
● 日本市場特有の“見えない壁”とは何か?
● それでもBYDに可能性を感じる理由とは?
という3つの視点から、リアルな現状と未来の可能性を掘り下げてきました。
結論として言えるのは、BYDが日本で売れていないのは「クルマが悪いから」ではないということ。
むしろ、走り、装備、価格、技術力――どれを取っても優れているのに、それが「まだ浸透していない」だけ。
日本人がクルマ選びに重視する「安心感」「信頼」「ブランド認知度」などの要素が、今のBYDにはまだ不足しているだけなのです。
僕自身も、最初は疑いの目で見ていました。でも、実際に乗ってみて、その印象はガラリと変わりました。
そして同じように、試乗した人、触れた人たちが「意外とアリ」「むしろいいじゃん」と言い始めているのを、肌で感じています。
これはつまり、今は“売れない理由”が注目されている段階だけど、近い将来には“売れない理由が消えていく”プロセスが始まるということ。
特にZ世代や、ブランドにとらわれない世代が増えていけば、BYDのような新しい価値を持ったクルマが“当たり前に選ばれる時代”が来ると確信しています。
今、BYDを気にしているあなたは、もしかしたら時代の一歩先を見ているのかもしれません。
“周囲がまだ知らないからこそ、自分で見て、感じて、判断する”――そんな視点が、新しい選択肢を広げてくれるはずです。
クルマの未来がEVにシフトしていく中で、BYDは間違いなく“キープレイヤー”の一つになります。
「中国車だから」「見かけないから」と避けるのではなく、一度フラットな気持ちで向き合ってみる価値のあるブランド。
それが今のBYDです。
今はまだ“売れていない”かもしれない。
でも、「売れない理由があったからこそ、それを乗り越えたときに強くなる」――
そんなストーリーをこれからのBYDは描いていくのだと思います。