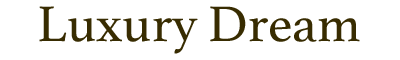BYD公式画像引用
「BYDって誰が買うの?」
正直、最初にそう思ったのは僕自身でした。長年車好きとして、そして小さな会社を経営する立場として、何台も車を乗り換えてきた経験がありますが、中国メーカーの車を選ぶなんて、一昔前なら考えもしませんでした。
それでも最近、「BYDを買った」「今度試乗してくる」といった声を耳にする機会が増えたんです。友人の経営者仲間の中でも、話題に上ることが増え、「BYDって実際どうなの?」という問いかけが日常的になってきました。そこで気になって調べてみたところ、「BYD 誰が買う?」というキーワードで検索している人がとても多いことを知りました。
たしかに、中国企業の車に対しては、まだまだ偏見や不安を持っている人が多いのも事実です。「壊れやすいんじゃない?」「性能って日本車に比べてどうなの?」「中国車なんて誰が買うの?」といった声は、実際に僕の周りでも何度も耳にしました。
ですが現実として、BYDを買う人は確実に存在し、しかもその数は着実に増えているんです。では、なぜ今このタイミングで「BYDの車を選ぶ人」が出てきているのか?その背景には、価格・性能・ブランド戦略、そして今の時代に合った価値観の変化が関係しています。
かく言う僕自身も、あるBYDの車に試乗してみて、正直ちょっと驚かされました。思っていたよりもはるかに質感が高く、走りも滑らか。「ああ、これが“いまどきの中国車”か」と思わされた瞬間でした。
もちろん不安要素がゼロなわけではありませんが、「誰が買うのか?」という問いに対しては、「こういう人たちが、こういう理由で選んでいる」と答えられるようになったと感じています。
この記事では、
・実際にBYDを買っているのはどういう人たちなのか?
・「中国車なのに」選ばれている理由とは何か?
・そして、今後BYDが日本でどう展開していくのか?
この3つのポイントを中心に、リアルな声や実体験を交えながら、僕なりの視点で解説していきます。この記事を読み終わる頃には、「BYD 誰が買うのか?」という疑問に対して、ひとつの答えが見つかるはずです。
BYD公式YouTube動画引用
BYD 誰が買う?実際の購入者像とその理由に迫る

BYD公式画像引用
「BYDって誰が買うの?」という疑問は、BYDというブランドが日本でまだ浸透していないからこそ、多くの人が抱く当然の感覚です。ましてや相手は中国メーカー。これまで日本車や欧州車が主流だった中で、あえて中国車を選ぶ人がいるなんて、少し前までは考えられなかったかもしれません。
しかし実際のところ、**BYDの車を選ぶ人たちは確実に存在しており、その層は一様ではありません。**若者、法人オーナー、環境意識の高い人々…さまざまな背景を持つ人たちが、自分なりの価値観や理由でBYDを選んでいます。
このセクションでは、実際にどんな人がBYDを買っているのか、その理由は何なのか、私の実体験や周囲の声を交えながら掘り下げていきます。
・BYDの車を買っているのはどんな人たち?実際の声から読み解く
→ 購入者層(若者、会社経営者、EV志向の人など)を紹介しつつ、自分の周りの声も交えて紹介。
・なぜ日本人が中国車BYDを選ぶのか?価格・性能・装備から見る魅力
→ 日本人にとってのコスパ感や、国産車との比較を交えた個人的な意見も加える。
・EVを選ぶ人が増えている理由とBYDのポジショニング
→ EVシフトの中でBYDの車がどう受け入れられているかを、ユーザーの変化と絡めて解説。
・周囲の評判はどう?「中国車なんて…」から変わる印象のギャップ
→ 体験談とともに、購入後の評価や予想外のポジティブな反応を紹介。
・「人とは違う選択」が価値になる時代にBYDを選ぶ心理
→ みんなと同じじゃない選択肢を求める人たちの傾向に注目し、その動きを紹介。
BYDの車を買っているのはどんな人たち?実際の声から読み解く
「BYDなんて誰が買うんだよ」と思っていた僕自身、最近になってその認識を見直す機会が増えてきました。特に印象的だったのは、知り合いの中小企業経営者がBYD ATTO 3を購入していたことです。話を聞いてみると、「補助金込みでこの価格なら、輸入車より断然コスパがいい。しかも普通に走りも良い」とのこと。
また、若者層、特に30代以下の層でBYDに興味を持つ人が増えているのも実感しています。SNSやYouTubeなどでBYDの試乗レビューが話題になっていることもあり、「なんとなく気になる」という軽い入り口から、試乗や見積もりに行く人が多いようです。中には「人生初の車がBYD」という人もいるほどです。
さらに、EVに興味を持ち始めた中高年層も、BYDを「試してみたい車」として挙げるようになってきました。EVへの買い替えを検討していた60代の知人は、国産EVよりも装備が充実していて価格が抑えられていることに惹かれたと話していました。
このように、BYDを選ぶ人たちは決して“奇をてらった物好き”ではなく、情報に敏感で、価値に対して合理的な判断をする人たちであると感じています。
なぜ日本人が中国車BYDを選ぶのか?価格・性能・装備から見る魅力
BYDの車が日本で注目され始めている一番の理由は、圧倒的なコストパフォーマンスにあると思います。たとえば、BYD ATTO 3は300万円台から購入可能で、補助金を利用すればさらに安くなります。その価格帯でありながら、電動パワーシート、360度カメラ、ナビ、サンルーフといった装備が標準装備というのは、国産車や欧州車ではなかなか見られません。
僕自身もATTO 3に試乗してみましたが、加速性能や静粛性には驚きました。内装の質感も、正直なところ「思ったより全然いいじゃん」という印象で、これでこの価格?と疑ってしまうほど。特にEVにありがちな「チープ感」が少ないのは大きな魅力です。
また、中国の都市部ではすでにBYDのEVタクシーが当たり前に走っており、実績という点でも安心感があるのは意外と知られていない事実です。国産車と比べると歴史こそ浅いものの、世界的にはすでにテスラと並ぶ存在になってきているのです。
つまり、日本人がBYDを選ぶ理由は「価格が安いから」だけではなく、「装備や性能も満足できるレベルにあるから」。そしてそのバランスが取れているからこそ、納得して購入する人が増えているのだと思います。
EVを選ぶ人が増えている理由とBYDのポジショニング
ここ数年で、僕の周囲でもEVに乗り換える人が増えてきました。特に都市部では充電インフラが整い始めていて、「もうガソリン車じゃなくてもいいかな」という声が自然に出てくるようになっています。その中でBYDは、手頃な価格でEVを手に入れられるブランドとして、しっかりとポジションを築いているように感じます。
テスラは魅力的だけど高すぎる。国産のEVは装備が物足りない。そんな声を多く聞く中で、BYDは「ちょうどいい」立ち位置にあると言えます。さらにBYDは、自社でバッテリーから車両まで一貫生産しており、その技術力は世界的にも高く評価されています。これは、EVを検討している人にとって非常に大きな安心材料です。
僕自身もEVには以前から興味がありましたが、価格や充電環境の不安でなかなか踏み切れませんでした。そんなとき、BYDの存在を知り、「この価格帯でEVに乗れるならアリかも」と初めて現実的に感じたんです。
BYDは、「高嶺の花だったEVを現実的な選択肢に変えてくれたブランド」だと、僕は思っています。
周囲の評判はどう?「中国車なんて…」から変わる印象のギャップ
最初に「BYD買ったよ」と聞いたとき、正直言って僕は驚きました。「中国車って大丈夫なの?」というのが率直な感想でした。でも、実際に乗ってみたり話を聞いたりしていくうちに、そのイメージが少しずつ変わっていくのを感じたんです。
「走りが静かでスムーズ」「内装がしっかりしている」「装備が豪華」といった声が、思った以上に多く聞こえてきました。中には「トヨタや日産のEVより全然いいかも」なんて声まであります。もちろん個人差はありますが、“試してみると意外と良い”というパターンが圧倒的に多いというのは事実です。
僕も実際に乗って感じたのは、「これが“いまの中国車”か」という驚きでした。かつての「安かろう悪かろう」とはまったく違う。今は「価格に対して得られる満足度が高い」という、コスパ重視の人に刺さるブランドになっていると思います。
まだ偏見は根強い部分もありますが、「乗った人の評価」は確実に変わりつつあります。
「人とは違う選択」が価値になる時代にBYDを選ぶ心理
今の時代、「あえて他の人と違う選択をする」ことに価値を感じる人が増えていると感じます。特に若い世代には、周りと同じであることよりも、「自分らしい選択」を重視する傾向があるように思います。そういう意味で、**BYDという選択肢は“通”な選び方”**と捉えられることも増えています。
僕の知人でも、「人と同じクルマは嫌」「どうせなら注目される方がいい」という理由でBYDを選んだ人がいます。実際に乗っていると、「それどこのクルマ?」「中国車なの?意外!」と会話のネタにもなりやすい。まだ珍しいからこそ、“先取り感”や“こだわり”が感じられる選択肢になっているんです。
今後、BYDがさらに認知されていけば、こういった「個性派層」だけでなく、より幅広い層に受け入れられていく可能性が高いと感じています。
BYD 誰が買うのか?と疑う人へ伝えたい本当の価値と未来
「BYDって、誰が本当に買うの?」という疑問。
正直、それは僕自身も最初に抱いた感想でした。
中国車と聞くと、どこか“信頼性に欠ける”“壊れやすい”“デザインが微妙”というような、ネガティブな印象を持っていたのは確かです。だけど今、その先入観が崩れつつあるのを自分でも感じています。
このセクションでは、そんな疑いを持っている方にこそ知ってほしい、BYDの「今の姿」と「これからの可能性」について掘り下げます。
体験からくる気づき、技術面の進化、安全性、そして時代の価値観の変化。
そのすべてを通じて、「BYDは誰が買うのか?」という問いに対して、より納得できる答えを導いていきます。
・中国メーカーに対するイメージと現実のギャップ
→ かつての“安かろう悪かろう”との決別、自身の先入観が覆された体験を紹介。
・技術的な実力は?BYDが評価される理由とは
→ 世界的な技術水準や実績、テスラとの比較も交えて解説。
・「安全性は大丈夫?」という声への答え
→ 実際の安全性能評価や装備、国産車との比較、乗ってみてどうだったかも語る。
・誰が買うのか?という視点から「これから誰が買うようになるか」へ
→ これからの世代や価値観の変化によって買う人が増える理由を予測。
・「BYDはアリ」だと気づく人が増えている理由
一度乗った人、試乗した人が手のひらを返すような反応になる例など、自分の感覚を交えて伝える。
中国メーカーに対するイメージと現実のギャップ
僕が初めて「中国車に乗ってみようかな」と思ったとき、正直かなり抵抗がありました。
「どうせ安かろう悪かろうだろう」「壊れやすそう」「見た目がダサいのでは?」といった偏見が頭をよぎりました。でもそれは、過去の中国製品に対する古い記憶や、ネットの噂話に引っ張られていた部分が大きかったと、今は感じています。
実際にBYD ATTO 3を見て、触れて、試乗してみたとき、その考えは一気に覆されました。
ドアを開けた瞬間の質感、シートの座り心地、ディスプレイの見やすさ、走り出しの滑らかさ…。
「え、これ本当に中国車?普通にすごくいいじゃん」と、思わず声に出してしまったほどです。
多くの人が未だに抱えている“中国車=低品質”というイメージは、過去のものでしかありません。実際に中国メーカーは、ここ10年で急速に進化しており、スマホや家電と同様に、自動車の分野でも世界に通用するレベルに達しています。
情報をアップデートしないと、本当に損する時代になってきているなと実感しました。
技術的な実力は?BYDが評価される理由とは
BYDが単なる“新興企業”ではないことは、少し調べればすぐに分かります。
2023年には世界最大のEV販売台数を誇り、テスラを上回る勢いで成長しています。特に注目すべきは、バッテリーの技術力の高さ。BYDは自社で「ブレードバッテリー」と呼ばれる安全性の高いリチウム鉄リン酸バッテリーを開発・製造しており、世界中のEVメーカーにも供給しています。
さらに、EVに必要なモーター、パワーコントロールユニット、プラットフォームまでを完全内製化しているのが強みです。つまり、EVに必要な「心臓部」を自社で一貫して作れる企業なんです。
これは、外部に頼らず高品質かつコスト効率の良い車づくりを可能にし、まさに**“EV界のトヨタ”**のような存在だと言えるかもしれません。
実際に乗ってみて感じたのは、加速のスムーズさや車内の静粛性の高さ。これは、テスラや国産EVと比べても引けを取らないレベルでした。しかも、その価格帯を考えればむしろ驚異的なコスパです。
「技術的に本当に信頼できるの?」という疑問に対しては、僕は自信を持って「YES」と言えます。
「安全性は大丈夫?」という声への答え
「中国車って安全なの?」という声は、今でもよく聞かれます。実は僕自身、試乗前に一番気になっていたのがこの点でした。
でも実際に調べてみると、BYDはEUの安全基準(ユーロNCAP)で最高評価の5つ星を獲得しているんです。これは、欧州車や日本車と同レベルの安全性能を意味します。
ATTO 3に乗ってみて感じたのは、最新の運転支援機能(ADAS)が非常にしっかりしていること。自動ブレーキ、レーンキープアシスト、360度カメラなど、必要な装備はすべて揃っていますし、操作も直感的で使いやすかったです。
内装の剛性感やボディの作りもしっかりしていて、「不安を感じるような部分」は全くありませんでした。
また、BYDはバッテリーの発火対策にも力を入れており、自社開発のブレードバッテリーはピン刺しテスト(物理的な衝撃)でも発火しないという結果を出しています。
これは、EVの普及において非常に重要な要素であり、実際のユーザーからも高い評価を得ているポイントです。
「安全性が不安」という気持ちはよく分かりますが、僕の体験を踏まえると、むしろ安心できる車に仕上がっているというのが率直な感想です。
誰が買うのか?という視点から「これから誰が買うようになるか」へ
今までは「BYDなんて誰が買うんだよ」と言われていましたが、**これからは“そういう時代じゃなくなる”**と僕は感じています。
今の若い世代は、「ブランド信仰」よりも「中身やスペック、価格のバランス」を重視する傾向が強い。だからこそ、BYDのような“見た目より実用性で選ばれる車”が受け入れられやすくなっているのです。
それに加えて、環境意識の高まりや政府の補助金制度など、EVにシフトする流れはどんどん強くなってきている。その流れの中で、価格と性能のバランスが取れたBYDは、次世代の主流になる可能性を十分に秘めています。
今はまだ「一部の人が買っている」という状況かもしれません。でもこれからは、「あえて国産車を選ばない理由」が増えていくはず。
そしてそのとき、「BYDを最初に選んだ人たち」が先駆者として語られるようになるかもしれません。
「BYDはアリ」だと気づく人が増えている理由
実際にBYDに触れた人、試乗した人の多くが共通して言うのが、
「思ってたより全然良い」「むしろ普通にアリじゃない?」という言葉です。
僕の知人の中でも、最初は否定的だった人が、試乗後に態度を一変させたケースが何件もあります。中には「次の車はBYDにしようかな」と言い出した人もいました。人間って、やっぱり実物を体感すると価値観が変わるんですよね。
それだけ、BYDの完成度や“裏切り感(いい意味で)”が高いということです。まだ世間の印象は追いついていないかもしれませんが、実際に触れた人の反応は、着実に変わってきています。
僕自身も、正直ここまで印象が変わるとは思っていませんでした。でも今は、誰かに「BYDってどうなの?」と聞かれたら、こう答えます。
「思い込みだけで判断しない方がいい。試乗してみたら、きっと考えが変わるよ」と。
まとめ:BYDは「誰が買うのか?」ではなく、「なぜ選ばれるのか?」の時代へ
「BYDなんて誰が買うの?」という疑問から始まったこのテーマ。
この記事では、実際にBYDを購入・検討している人たちの実像や、なぜ中国車であるBYDが選ばれているのかという背景、そしてその“選ばれる理由”を深掘りしてきました。
結論として言えるのは、BYDはもう“得体の知れない中国メーカー”ではないということ。
EVとしての性能、装備、安全性、そして価格。そのすべてのバランスが極めて高く、合理的にクルマを選ぶ人たちにとって、「選ばない理由がない」レベルに達しています。僕自身も試乗を通じてその完成度を体感し、率直に驚かされました。
そして今、BYDを選ぶ人たちは、
「人と違う選択を楽しむ人」
「環境意識の高い人」
「コスパを冷静に見極める人」
「新しい価値を柔軟に受け入れられる人」
そんな“変化に敏感な層”が中心です。ですが、これからはより一般的な選択肢として、多くの人が「アリかも」と感じ始める時代が来るでしょう。
かつては“誰が買うんだ?”と疑われた存在が、今は“なるほど、こういう人が買うのか”と認識され、やがて“自分も買うかも”へと変わっていく。そんな兆しを、僕はBYDというブランドに感じています。
クルマ選びの基準は、時代とともに変わります。
「国産だから安心」「輸入車だから高級」という時代ではなく、「自分にとって納得できる価値があるか」が、これからのモノ選びの本質です。
BYDという選択肢は、まさにその象徴のような存在。
そしてこの記事が、「BYD 誰が買うのか?」という疑問に対する一つの答えとして、あなたの参考になれば嬉しいです。